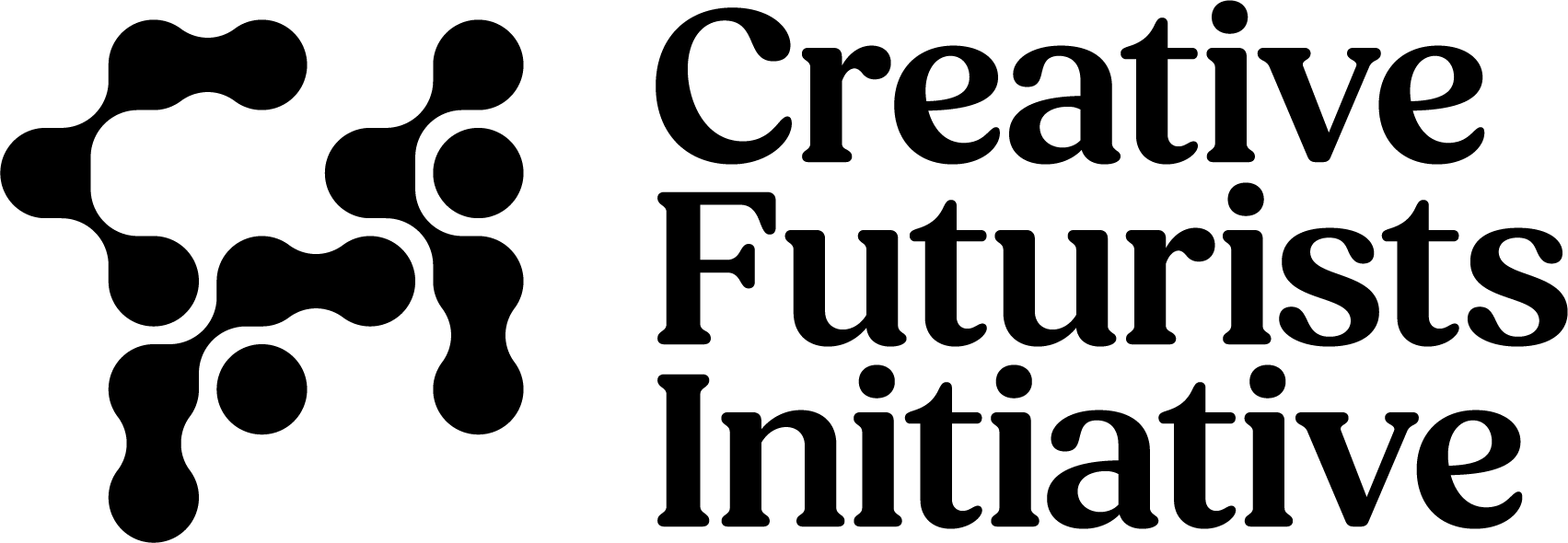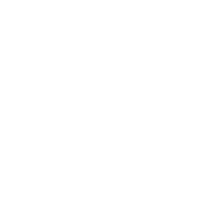差異を並べて味わう《私たちを計量しないために》《バイアス推理カード》|『TECH BIAS -テクノロジーはバイアスを解決できるのか?』:インタビュー 東京大学とソニーグループ株式会社による「越境的未来共創社会連携講座(通称:Creative Futurists Initiative、以下CFI)」では、8ヶ月間にわたる講座内の実践研究プロジェクトの成果発表として、2024年11月23~25日の3日間、東京大学本郷キャンパスにおいて「Tech Bias —テクノロジーはバイアスを解決できるのか?」展を開催。出展した4グループのみなさんにインタビューを行ないました。今回は、身近な製品設計にも関わる「標準的身体」と「計量(数字で扱うこと)」について捉え直す《私たちを計量しないために》と、バイアスについてオープンに語らうコミュニケーションの仕組みを作る《バイアス推理カード》についてお話を伺いました。(※) 記事中の所属・役職等は取材当時のものTEXT: Nanami Sudo PHOTOGRAPH: KAORI NISHIDA PRODUCTION: VOLOCITEE Inc.目次: 標準の大きさ・形とは何かを疑ってみる 手にまつわる記憶から自分の個性を見つめる ゲームでテクノロジーに潜むバイアスを考察する 標準の大きさ・形とは何かを疑ってみるこちらの作品のテーマは「標準的身体」です。ある製品において想定される「人間の手はこれくらいの大きさや形である」という設定に対して、それがいかにして標準的と言えるのか? という問いを立てました。推論ですが、世界の製品の多くは、おそらく西洋の成人男性の健常者が基準になっていると思います。しかし、西洋の成人男性の健常者の中にもばらつきがありますよね。 ピアノを例に挙げると、1オクターブの幅が165.5mmに規格化されていますが、手の小さい方では、指が届きにくいため弾くことが困難です。メンバーの一人は以前ピアノを習っていたけれど、先生から「手が小さいから無理」と言われて辞めてしまったそうです。しかし、実は音階を保つために、鍵盤のサイズなどの構造が関係しているわけではないんです。ピアノの設計は、長い歴史を持っていて格式高いということも、この規格を固定化してしまっている一つの要因として挙げられると思います。それが今に至るまで、何となく当たり前として受け入れられてきて、意識されてこなかったのかもしれません。モーツァルトら著名な作曲家たちがどんな体格だったのかは正確には分かりませんが、過去の演奏者の多くが男性だったという背景も関係し、ピアノの設計にも西洋の成人男性の平均的な体格が影響しているのではないでしょうか。さらには、ピアノを嗜むことが格式や教養を示すものであり、それが男性に偏っていたのではないかということも推測できます。 また、会場には五本指の軍手も例として掲示しました。3Dプリンターで「手尺1尺=約30.3cm=標準」と設定した手の模型を作成し、そこに軍手をはめてみました。今回展示をしてみて、来場者の方との会話の中で、この形が必ずしも全ての人に合うわけではないことに改めて気づかされました。「指が短いから、手袋をはめると先端が余ってしまい、その瞬間に自分の手が標準とは違うのだと感じる」という話も伺いました。特に指の長さや形状、手の大きさによってはフィットしない場合があります。そもそも五本指を標準とすることについても再考する余地があるように思います。また、今回作成した模型は関節が曲がらないため、これに軍手をはめようとすると非常に難しいことにも気づき、人間の手の動きの自由度や柔軟性についても、当たり前ではないと再認識させられました。 さらに「手袋や衣服の標準は地域や文化によって異なるのではないか」という指摘もありました。今回の展示を通じて、そうした多様性や個々の身体に合わせた製品設計の必要性を実感することができました。これは、身近な道具の設計にも通ずる部分があると思います。多くの人にとって「標準的」とされるサイズで作られているものでも、実際には身体のパーツが大きい人や小さい人、子どもや高齢者にとっては、その設計が負担になってしまうこともあります。まずは「標準」を疑ってみる視点が、私たちの生活をより良くするきっかけになるのではないでしょうか。…